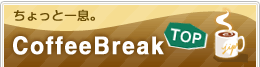新刊書紹介
新刊書紹介
オープンイノベーション時代の技術法務 スタートアップの知財戦略と ベストプラクティス
| 編著 | 鮫島 正洋 編集代表 |
|---|---|
| 出版元 | 日本加除出版 A5判 392p |
| 発行年月日・価格 | 2024年6月発行 4,840円(税込) |
本書は,知財戦略と契約実務をボーダレスにこなすスタイル(=技術法務)を追求してきた著者によるケーススタディ集である。副題にスタートアップとあるが,スタートアップの事例のみでなく,内容はバラエティーに富んでいる。また,事例における弁護士には「クリエイティブなインテリジェント」が感じられる。知財関係者に広くお勧めしたい所以だ。
本書のメインパートである第2章には,18の事例が集められている。各事例は,クライアントと弁護士の会話を基調として,末尾に「技術法務のポイント」という要約が付けられており,読み易い。しかしそれだけではない。「ここでの考え方」における解説や提案は知財実務者に向けたものであり,読み応えがある。事例によっては「COLUMN」が挿入され,情報が追加されていて,さらに充実している。
事例の多彩さにも目を見張る。紹介者は製造業の知財部門に勤務しており,序盤は比較的馴染みのある領域である。一方,「事例8 生成AIモデルを利用したビジネスモデルの権利保護を検討した事例」を含む3事例は,デジタル領域の事例であり,この領域に詳しくない紹介者は啓発された。また,事例14はソフトウェア開発でありがちと思われる契約不適合の問題を扱い,事例15と事例16は商標を,事例17と事例18は出資とデューデリジェンスを扱っていて,いずれも興味深い。
事例が多彩というだけではない。例えば事例2では,顧客から提示されたビジネスモデルのうち,特許権が取得可能なビジネスモデルを提案し,顧客のビジネス展開を意識した契約書を作り込んでいく様子が描かれている。事業理解の解像度を高めて,契約や知財戦略の提案をしていくことは,スタートアップにのみ求められることではないだろう。
第3章は,顧客・VC・大学といったステークホルダーへのインタビュー集として,第2章を補完する。その中で著者と一緒に仕事をした顧客の一人の言葉が印象深い。「本当に面白かったです」。彼は「スタートアップが持っているのは,卵なんです」「卵は壊れやすいものです」とも言う。それを扱うために「21世紀に本当に重要なのは,クリエイティブなインテリジェントです」と別のインタビュイーは答える。「卵」はどの企業にもあるはずだ。
本書は「技術法務」の第2作である。第1作は2014年に出版され,本書は2024年に出版された。「本書の出版をもって,「技術法務で,日本の競争力に貢献する」という弊所の社是を実現していきたい」と編集代表は述べていて熱い。知財,法務部門の担当者も本書で得た知見を駆使することで自社の競争力向上に貢献できるであろう。
本書のメインパートである第2章には,18の事例が集められている。各事例は,クライアントと弁護士の会話を基調として,末尾に「技術法務のポイント」という要約が付けられており,読み易い。しかしそれだけではない。「ここでの考え方」における解説や提案は知財実務者に向けたものであり,読み応えがある。事例によっては「COLUMN」が挿入され,情報が追加されていて,さらに充実している。
事例の多彩さにも目を見張る。紹介者は製造業の知財部門に勤務しており,序盤は比較的馴染みのある領域である。一方,「事例8 生成AIモデルを利用したビジネスモデルの権利保護を検討した事例」を含む3事例は,デジタル領域の事例であり,この領域に詳しくない紹介者は啓発された。また,事例14はソフトウェア開発でありがちと思われる契約不適合の問題を扱い,事例15と事例16は商標を,事例17と事例18は出資とデューデリジェンスを扱っていて,いずれも興味深い。
事例が多彩というだけではない。例えば事例2では,顧客から提示されたビジネスモデルのうち,特許権が取得可能なビジネスモデルを提案し,顧客のビジネス展開を意識した契約書を作り込んでいく様子が描かれている。事業理解の解像度を高めて,契約や知財戦略の提案をしていくことは,スタートアップにのみ求められることではないだろう。
第3章は,顧客・VC・大学といったステークホルダーへのインタビュー集として,第2章を補完する。その中で著者と一緒に仕事をした顧客の一人の言葉が印象深い。「本当に面白かったです」。彼は「スタートアップが持っているのは,卵なんです」「卵は壊れやすいものです」とも言う。それを扱うために「21世紀に本当に重要なのは,クリエイティブなインテリジェントです」と別のインタビュイーは答える。「卵」はどの企業にもあるはずだ。
本書は「技術法務」の第2作である。第1作は2014年に出版され,本書は2024年に出版された。「本書の出版をもって,「技術法務で,日本の競争力に貢献する」という弊所の社是を実現していきたい」と編集代表は述べていて熱い。知財,法務部門の担当者も本書で得た知見を駆使することで自社の競争力向上に貢献できるであろう。
(紹介者 会誌広報委員 H.K.)
知財紛争“和解”の実務
| 編著 | 三山峻司 編著,西野卓嗣,室谷和彦, 池田聡,矢倉雄太,西川侑之介 著 |
|---|---|
| 出版元 | 中央経済社 A5判 352p |
| 発行年月日・価格 | 2024年6月27日発行 4,180円(税込) |
知財高裁ホームページの統計によると,平成26年〜令和4年の東京地裁と大阪地裁での特許権侵害訴訟の終局事由の約3割が和解であり,約6割が判決(認容判決が約2割,棄却判決が約4割)となっている。単純にこの数字だけで比べれば,和解の割合を低いと見る向きもあるかも知れない。だが,知財紛争の中でも特許権侵害訴訟は,当事者の対立が大きく和解による解決が難しい傾向にあること,また訴訟前の交渉段階で和解に至る事案も多数存在することから,知財紛争全体で見れば,和解による解決の割合はより高いものと考えられる。したがって,特に渉外的な業務に携わる知財担当者は,和解による紛争解決も念頭に置き,この実務対応について理解しておく必要がある。
しかしながら,知財紛争に関して,訴訟への対応を解説する実務書やセミナーは多いものの,和解にフォーカスしたものはあまり目にしない。これは,裁判による決着で判決文が公開される事案に比べ,和解で終結した紛争では当事者による情報開示も限定的なため,第三者が情報を得ることは基本的に困難であり,先例による知見が少ないことからすれば無理からぬこととも思われる。だが,本書はそのような和解による知財紛争の解決について,著者らの経験等に基づいて実務対応のポイントを解説した貴重な書籍である。
構成としては,まず第1章で「当事者視点(課題中心アプローチ)」として,当事者双方の立場から,限られた時間と情報の中でベターな解決策を見出すアプローチの重要性を確認し,第2章と第3章では訴訟前の交渉段階と訴訟係属中での和解について,場面ごとの警告書や回答書の雛型を例示しつつ,状況に応じた留意点を論じている。続く第4章と第5章では調停や仲裁における和解条項を解説し,最後に第6章で「Episodeで考える和解」と題して,8つの事例をもとに様々な角度から和解の得失を検討している。なお,このEpisodeはいずれも時系列で区切りながら事案の進展に沿って各段階でのポイントの解説が挟まれており,かつ登場人物の立場や心理にも言及されていることから,自分が当事者としてその事案を追体験するような感覚で,状況ごとの留意点を理解することができるものとなっている。さらに本書の随所に挿入された,著者らの経験を踏まえた実感等を紹介するコラムも大変参考になるものである。
前述の通り和解について公開された情報が少ない中で,特許権,表示,デザイン,著作権など各種ケースにおける先例からの知見を得られる有用な情報源として,知財紛争への対応を学びたい方にはぜひ読んでもらいたい一冊である。
しかしながら,知財紛争に関して,訴訟への対応を解説する実務書やセミナーは多いものの,和解にフォーカスしたものはあまり目にしない。これは,裁判による決着で判決文が公開される事案に比べ,和解で終結した紛争では当事者による情報開示も限定的なため,第三者が情報を得ることは基本的に困難であり,先例による知見が少ないことからすれば無理からぬこととも思われる。だが,本書はそのような和解による知財紛争の解決について,著者らの経験等に基づいて実務対応のポイントを解説した貴重な書籍である。
構成としては,まず第1章で「当事者視点(課題中心アプローチ)」として,当事者双方の立場から,限られた時間と情報の中でベターな解決策を見出すアプローチの重要性を確認し,第2章と第3章では訴訟前の交渉段階と訴訟係属中での和解について,場面ごとの警告書や回答書の雛型を例示しつつ,状況に応じた留意点を論じている。続く第4章と第5章では調停や仲裁における和解条項を解説し,最後に第6章で「Episodeで考える和解」と題して,8つの事例をもとに様々な角度から和解の得失を検討している。なお,このEpisodeはいずれも時系列で区切りながら事案の進展に沿って各段階でのポイントの解説が挟まれており,かつ登場人物の立場や心理にも言及されていることから,自分が当事者としてその事案を追体験するような感覚で,状況ごとの留意点を理解することができるものとなっている。さらに本書の随所に挿入された,著者らの経験を踏まえた実感等を紹介するコラムも大変参考になるものである。
前述の通り和解について公開された情報が少ない中で,特許権,表示,デザイン,著作権など各種ケースにおける先例からの知見を得られる有用な情報源として,知財紛争への対応を学びたい方にはぜひ読んでもらいたい一冊である。
(紹介者 会誌広報委員 H.A.)