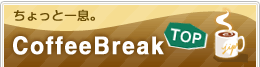新刊書紹介
新刊書紹介
清水節先生古稀記念論文集
多様化する知的財産権訴訟の未来へ
| 編著 | 大鷹一郎,田村善之 編集代表 |
|---|---|
| 出版元 | 日本加除出版 A5判 1,032p |
| 発行年月日・価格 | 2023年10月発行 17,600円(税込) |
本書は清水節元知的財産高等裁判所長の古稀を記念して発行された論文集である。清水先生の功績として著名なものには,ピリミジン誘導体事件大合議判決や,TRIPP TRAPP事件判決が挙げられる。ピリミジン誘導体事件については本書の『進歩性判断に何故「本件発明の課題」が影響するのか?(高石秀樹)』に詳しい。
構成は5章からなり,第1章が総論,第2章が特許法,第3章が著作権法,第4章が意匠法・商標法・不正競争防止法,第5章がその他である。特許法に関してはさらに,基本概念(発明,発明者,当事者),特許要件等,権利行使,無効審判・審決取消訴訟の4節に分かれている。一つ一つの論文は概ね10~15ページであるが,中には20ページを超えるものもあり大変読み応えがある。その中から,前提となる知識があまりなくても読め,すぐに実務に取り入れられそうだと感じた論文を2つ紹介する。
1つ目は第1章の『知財訴訟における争点整理の在り方(武宮英子)』である。特に技術型の訴訟では,膨大な主張書面や書証の提出による争点整理の困難さから審理・判決に負荷がかかっていることに触れ,特許侵害訴訟における争点整理の工夫について提案したものである。「主張整理一覧表」を用いた争点整理の方法と実際の一覧表の例が挙げてあり分かりやすい。
2つ目は第2章第2節の『公然実施された製品から把握される発明(公然実施をされた発明)について(濱田百合子)』である。判示をもとに公然実施をされた発明について解り易く解説されており,「本件発明の技術的思想との同一性を意図しているかどうかではなく,本件発明の構成要件を具備する実施品が存在するという事実をもって,本件発明は公然実施発明と同一であると認定されたもの」との解説では,これまで曖昧だった公然実施に対する理解が深まった。
巻頭,高林龍弁護士・早稲田大学名誉教授によるお祝いの言葉として「このような魅力にあふれる清水さんであるからこそ,この度は,古稀をお祝いして多くの方々が参集して,立派な古稀記念論文集が刊行されることになりました。」とあるように,執筆者は前知的財産高等裁判所部総括判事の菅野雅之現仙台高等裁判所長官をはじめ,弁護士,弁理士,判事,教授など総勢65名にものぼり,清水先生の人望が窺える。
本書は実用書として非常に勉強になるのはもちろん,興味の赴くままにページを開くと,これまで意識していなかった判例や考えることのなかった数々の知財訴訟に触れることができる。初めはその厚さに圧倒されるが,読み進めるにつれて理解が深まり,まるで大学の講義を受けたかのような気分を味わえる1冊である。知財初心者の方にも是非手に取っていただき,奥深い知財訴訟の世界に浸っていただきたい。
構成は5章からなり,第1章が総論,第2章が特許法,第3章が著作権法,第4章が意匠法・商標法・不正競争防止法,第5章がその他である。特許法に関してはさらに,基本概念(発明,発明者,当事者),特許要件等,権利行使,無効審判・審決取消訴訟の4節に分かれている。一つ一つの論文は概ね10~15ページであるが,中には20ページを超えるものもあり大変読み応えがある。その中から,前提となる知識があまりなくても読め,すぐに実務に取り入れられそうだと感じた論文を2つ紹介する。
1つ目は第1章の『知財訴訟における争点整理の在り方(武宮英子)』である。特に技術型の訴訟では,膨大な主張書面や書証の提出による争点整理の困難さから審理・判決に負荷がかかっていることに触れ,特許侵害訴訟における争点整理の工夫について提案したものである。「主張整理一覧表」を用いた争点整理の方法と実際の一覧表の例が挙げてあり分かりやすい。
2つ目は第2章第2節の『公然実施された製品から把握される発明(公然実施をされた発明)について(濱田百合子)』である。判示をもとに公然実施をされた発明について解り易く解説されており,「本件発明の技術的思想との同一性を意図しているかどうかではなく,本件発明の構成要件を具備する実施品が存在するという事実をもって,本件発明は公然実施発明と同一であると認定されたもの」との解説では,これまで曖昧だった公然実施に対する理解が深まった。
巻頭,高林龍弁護士・早稲田大学名誉教授によるお祝いの言葉として「このような魅力にあふれる清水さんであるからこそ,この度は,古稀をお祝いして多くの方々が参集して,立派な古稀記念論文集が刊行されることになりました。」とあるように,執筆者は前知的財産高等裁判所部総括判事の菅野雅之現仙台高等裁判所長官をはじめ,弁護士,弁理士,判事,教授など総勢65名にものぼり,清水先生の人望が窺える。
本書は実用書として非常に勉強になるのはもちろん,興味の赴くままにページを開くと,これまで意識していなかった判例や考えることのなかった数々の知財訴訟に触れることができる。初めはその厚さに圧倒されるが,読み進めるにつれて理解が深まり,まるで大学の講義を受けたかのような気分を味わえる1冊である。知財初心者の方にも是非手に取っていただき,奥深い知財訴訟の世界に浸っていただきたい。
(紹介者 会誌広報委員 E.M.)