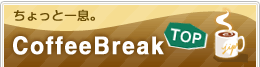新刊書紹介
新刊書紹介
33のテーマで読み解く意匠法
| 編著 | 峯 唯夫 著 |
|---|---|
| 出版元 | 勁草書房 A5判 240p |
| 発行年月日・価格 | 2023年7月発行 2,750円(税込) |
著者の峯氏は,弁理士試験委員(意匠),中央大学法学部兼任講師を長年務め,著書・論文も多数あり,意匠を得意とされている弁理士である。意匠法を苦手に感じている方にも意匠・意匠法を身近に感じてもらうために,本書を執筆されたとのことである。
本書の構成としては,大きな論点別に6章(Chapter)立てにして,各々にいくつかのユニット(Unit)をぶら下げて全33ユニットとし,各ユニットは基本的に「設題」「検討のポイント」「参照条文」「解説」「設題の検討」のように構成してあり,終わりにコラム的な「実務のためのひとこと」を添えている。また参照条文だけでなく,審査基準,特許庁編産業財産権法逐条解説(青本),斎藤瞭二氏「意匠法概説[補訂版]」(有斐閣),高田忠氏「意匠」(有斐閣)の解説を引用しており,また最高裁と知財高裁の著名判例も取り上げて丁寧に解説している。
通して読むのではなく,ユニットを選んでユニットごとに読んでもよくわかる構成となっている。各ユニットの正確な理解に必要な内容は網羅されており,多忙な方は通勤電車で読んでもよし,意匠の実務をされている方は辞書的に活用してもよしであろう。特に「実務のためのひとこと」が印象に残った。自分の得手不得手でよく理解できる内容,しっくり理解できない内容など理解レベルはさまざまであろうが,「実務のためのひとこと」で実務上のポイントを読者によく響くように書いていただいている。
どのユニットも興味深い勉強になる記載となっているが,例えばユニット4「意匠と発明」は,検討のポイントとして,意匠と発明考案の関係,意匠権と特許権の相互補完,意匠法5条3項(不可欠形状)を挙げている。また「実務のためのひとこと」としては,技術者の開発は「発明」,デザイナーの開発は「意匠」との,よくありがちな切り分けは意味がないことについて解説している。私にはこの「実務のためのひとこと」に加えて,「開発された内容を客観的に把握して,技術の側面からの保護,美的な側面からの保護の何れが適しているのかを考える必要があります。」と述べていることが非常に参考になった。自分の実務においては,日頃は特許による保護ばかりに意識が向いているような気がしており,美的側面からの保護として意匠も活用すべきであるな,と思いを新たにしたところである。
意匠法は,特許法と比較すると実務を担当されている方は少ないかもしれないが,本書に書かれているように,特許法(実用新案法),商標法,不正競争防止法,著作権法と,知財の主要法域に相当程度オーバーラップしているため,意匠法の担当でない方も本書を一読して,ご自身の担当法域との関連や抵触などを改めて把握しなおし,実務に当たるとよいのではと思う。価格も手頃で,お薦めの一冊です。
本書の構成としては,大きな論点別に6章(Chapter)立てにして,各々にいくつかのユニット(Unit)をぶら下げて全33ユニットとし,各ユニットは基本的に「設題」「検討のポイント」「参照条文」「解説」「設題の検討」のように構成してあり,終わりにコラム的な「実務のためのひとこと」を添えている。また参照条文だけでなく,審査基準,特許庁編産業財産権法逐条解説(青本),斎藤瞭二氏「意匠法概説[補訂版]」(有斐閣),高田忠氏「意匠」(有斐閣)の解説を引用しており,また最高裁と知財高裁の著名判例も取り上げて丁寧に解説している。
通して読むのではなく,ユニットを選んでユニットごとに読んでもよくわかる構成となっている。各ユニットの正確な理解に必要な内容は網羅されており,多忙な方は通勤電車で読んでもよし,意匠の実務をされている方は辞書的に活用してもよしであろう。特に「実務のためのひとこと」が印象に残った。自分の得手不得手でよく理解できる内容,しっくり理解できない内容など理解レベルはさまざまであろうが,「実務のためのひとこと」で実務上のポイントを読者によく響くように書いていただいている。
どのユニットも興味深い勉強になる記載となっているが,例えばユニット4「意匠と発明」は,検討のポイントとして,意匠と発明考案の関係,意匠権と特許権の相互補完,意匠法5条3項(不可欠形状)を挙げている。また「実務のためのひとこと」としては,技術者の開発は「発明」,デザイナーの開発は「意匠」との,よくありがちな切り分けは意味がないことについて解説している。私にはこの「実務のためのひとこと」に加えて,「開発された内容を客観的に把握して,技術の側面からの保護,美的な側面からの保護の何れが適しているのかを考える必要があります。」と述べていることが非常に参考になった。自分の実務においては,日頃は特許による保護ばかりに意識が向いているような気がしており,美的側面からの保護として意匠も活用すべきであるな,と思いを新たにしたところである。
意匠法は,特許法と比較すると実務を担当されている方は少ないかもしれないが,本書に書かれているように,特許法(実用新案法),商標法,不正競争防止法,著作権法と,知財の主要法域に相当程度オーバーラップしているため,意匠法の担当でない方も本書を一読して,ご自身の担当法域との関連や抵触などを改めて把握しなおし,実務に当たるとよいのではと思う。価格も手頃で,お薦めの一冊です。
(紹介者 会誌広報委員 I.N.)
AI時代の知的財産・イノベーション
| 編著 | 早稲田大学次世代ロボット研究機構
AIロボット研究所 知的財産・イノベーション研究会 森 康晃 編 |
|---|---|
| 出版元 | 日科技連出版社 A5判 216p |
| 発行年月日・価格 | 2023年7月19日発行 3,300円(税込) |
本書は,早稲田大学理工学術院で知的財産やイノベーションの科目を講義する講師の方々が中心となって執筆されたものである。
大学院や大学の学生だけでなく,企業で実務に当たっている方に向けて,ビジネスの最前線で理解しておかなければならないイノベーション論や知的財産について,基礎から応用的な内容がまとめられている。
全5章で構成されているが,第1章から第3章は,それぞれ「AIと知財」,「海外におけるAIと知財政策」,「イノベーションと起業」というテーマで,AIや知的財産の概要説明や,世界や日本におけるAIの技術・政策動向,イノベーション論について解説されている。知的財産については初学者向けの内容も多く,実務者にはやや物足りない感もあるかもしれないが,AI,知的財産,イノベーション論の概要を学べる内容となっている。
第4章は,「AI時代におけるバイオビジネス特許」というテーマで,医薬品分野に特化した章となっている。医薬品分野は,医療制度や薬事行政との関係もあり,他の分野とも大きく異なる点があることから,異なる点を中心に解説646されている。コロナウイルスによるパンデミックへの対応として活用が検討されたパテントプールの手法や,先進国と途上国のライセンス供与における利害の対立,生物多様性条約の枠組みや動向についても概説されている。私にとっては専門外で不慣れな分野であるが,全体像の理解に役立つ内容であった。
第5章は,「AIによる知財権侵害の法的規制の考え方」というテーマで,個人的に最も関心を持って読んだ章である。
AIは創造的な仕事を行えるだけでなく,情報やデータの処理において,他者の知財権を侵害し,損害をもたらす行為を行う可能性もある。AIが知識の革新を促進する役割をより発揮するためには,創造の成果を保護するとともに,知財権の侵害活動を法律により規制する必要もあるということで,AIによる侵害とその規制について解説されている。著者によると,これまで十分に重視されておらず,深い理論研究がなされていないということだが,既存の権利侵害責任制度を直接または拡張して適用する,もしくは,AIのための法的責任体制を新たに確立するという,2つの視点で考察されており,本問題を体系的に理解することができる。
AI,データ活用が盛んとなってきている中で,AIを活用したビジネスを検討されている方や,この領域における知財関連の問題を学びたい方に紹介したい書である。
(紹介者 会誌広報委員 K.K.)